京都新聞・神戸新聞・産経新聞に河合塾によるコラム連載(第9回)
2022年01月13日
京都新聞、神戸新聞と産経新聞に、京都大・大阪大・神戸大など関西の難関大受験をテーマとしたコラムの連載しています。本連載では、河合塾近畿地区の講師やスタッフが難関大受験に役立つ情報をお届けします。
今回ご紹介する第9回目は、河合塾数学科講師の中田正宏先生が神戸大学入試の数学を振り返ります。
神戸大学入試の数学を振り返る ~標準的問題で理解度、思考力をみる~
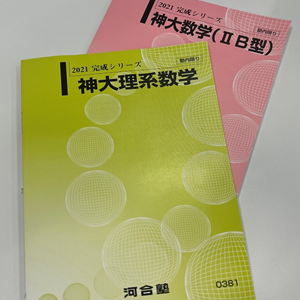
神戸大入試の数学は京都大や大阪大に比べると標準的で解きやすいように見えますが、問題自体はどれもよく練られています。目新しい問題も多数あり、数学の学力差がそのまま点数に反映される問題が多いように思います。
▶神戸大は出題の意図について、「標準的な問題を出題することで、基礎事項の理解度、正しく論証や計算を行う力をみる」と発表しています。しかも、「難問を排し」と前置きしています。
これは数学の理解度や計算力をみるには、最初の一歩が踏み出しにくい難問よりも、ある程度手のつけやすい標準的な問題の方が適しているからだと思われます。しかし、どこにでもあるような典型的な問題ではなく、問題集などに載せたくなるような新鮮でセンスの良い問題が今までに数多く出題されています。
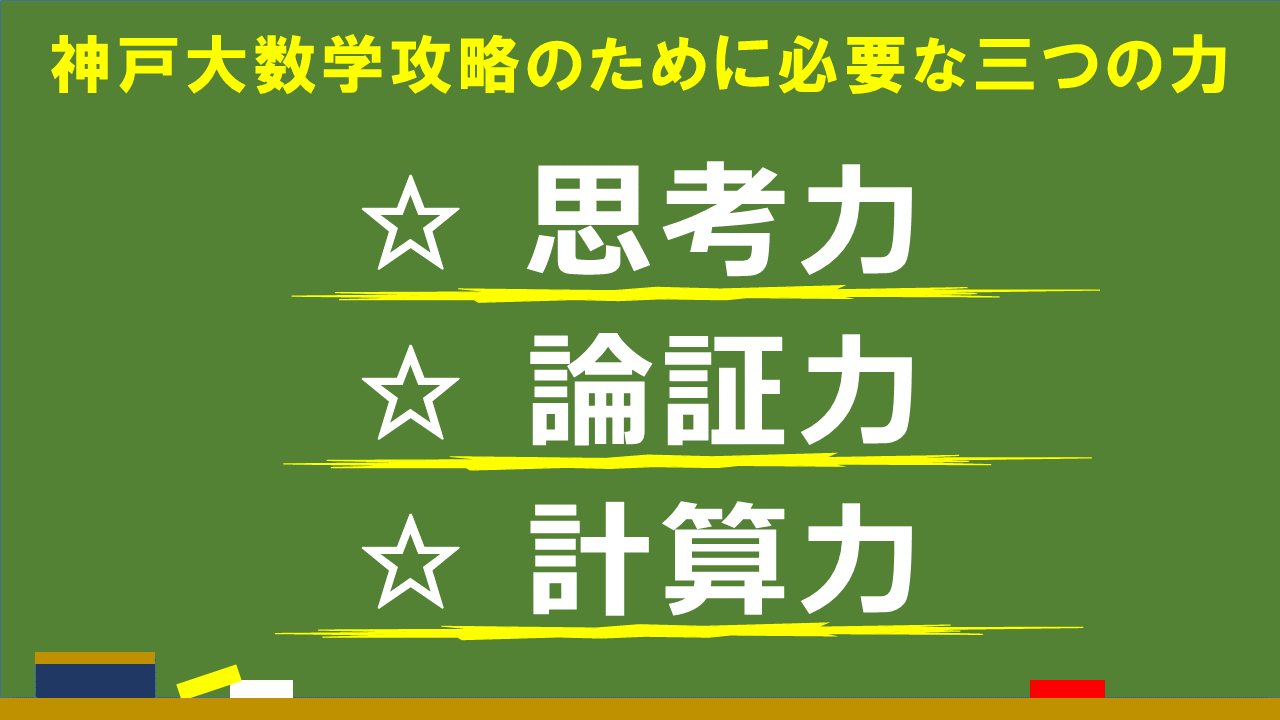
▶神戸大入試数学の特徴としては、
○文系は大問3題、理系は大問5題と、少ない問題数の中でさまざまな分野について理解度を問いたいため、複数の分野の融合問題で出題する。
○題意を把握することが難しい問題は少なく、与えられた関数や式にも煩雑なものは少ない。
○「~を示せ」という論証問題が多い。
○理系・文系ともにベクトルなどの図形問題、確率、数列からの出題が比較的多く、理系では数学Ⅲから2題程度が毎年出題される。
などが挙げられます。
▶2021年度入試を振り返ると、これらの特徴が当年度も踏襲されていました。さらに、文系では共通テストの影響を受けたかのような問題が出題され、理系ではコロナ禍における現役受験生の学習状況を考慮したと思われる数学Ⅲの問題が出題されました。また、例年多く出題される論証問題は少なめでした。
しかし来年以降も、前に述べた神戸大の出題の意図は変わることがないと思われますので、思考力、論証力、計算力を鍛えておかなければなりません。そのためには一問一問を丁寧に考え、しっかりとした答案を作成し、最後まで正しい計算を行う学習を継続しなければなりません。ややレベルの高い問題が出題された年もあるので、そのような問題に取り組んでおくことも大切ですが、まずは標準的な問題を最後まで解き切る練習を最優先にしてください。(河合塾数学科講師 中田正宏)
執筆者のプロフィール

▶河合塾数学科講師 中田正宏
大学受験科・高校グリーンコースでは、医学部・阪大・神大レベルといったトップレベルからハイレベルまでの講座を幅広く担当しています。ゼミ形式の講座では生徒一人ひとりへのきめ細かな指導で、生徒からの信頼が厚い講師です。また、神大オープン模試の作成チーフを務め、全統高2模試や高3生・高卒生対象のテキスト作成にも携わっており、入試情報に広く精通しています。
※ 2022年1月掲載時点

