京都新聞・神戸新聞・産経新聞に河合塾によるコラム連載(第17回)
2022年09月08日
京都新聞、神戸新聞と産経新聞に、一昨年から導入された共通テスト傾向分析のほか、京都大・大阪大・神戸大など関西の難関大受験をテーマとしたコラムの連載しています。本連載では、河合塾近畿地区の講師やスタッフが大学受験に役立つ情報をお届けします。
今回ご紹介する第17回目は、河合塾英語科講師の佐野光宜が京都大入試英語を振り返ります。
2022年度の京都大入試英語~指示内容を確認しながら読む~
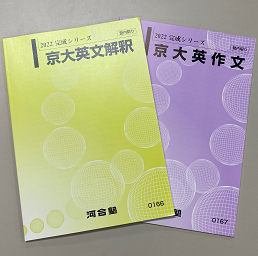
「大学入学共通テスト」の導入2年目となった令和4年度入試ですが,英語に関しては大きな設問形式の変更もなく、リーディング・リスニングともに前年度の平均点をやや上回る結果となりました。読者の方にはすでにご存じの方も多いかもしれませんが、共通テスト英語のリーディングで出題されるのはすべて読解問題で、センター試験時代には問われていた4択空所補充型の文法問題などは出題されません。これが京都大学受験生の答案の出来不出来に影響を与えたのではないかと思われる事態が2022年度の京都大学入試の読解問題で生じました。以下、その点を中心に振り返っていきたいと思います。
京都大学入試の読解問題では、近年、自然科学系の文章と人文科学系の文章からそれぞれ1題ずつ出題されるという形式が続いています。設問は大問Ⅰ・Ⅱ合わせて、英文和訳問題が4題、説明問題が2題でした。さて問題は、共通テストで文法問題が出題されなくなった影響です。河合塾では毎年、実際に京都大学を受験してきた生徒に当日どのような答案を書いたのか再現してもらい(再現答案)、河合塾による基準で採点を行ったうえで分析を行っています。今年度の再現答案を分析していて象徴的だと感じた事態は大問Ⅰの設問(2)で生じていました。この設問は英文和訳問題なのですが、その英文は、Such is the paceと始まり、途中にthat there are ...という部分があります。これはSuch is S that ...「Sはあまりにはなはだしいので…」という表現で、倒置が生じたやや複雑な形ではあるのですが、英文法の問題集などに取り組んでいれば出会う表現です。多くの答案は「そのようなものは速度であり…」などと訳し大きく誤解したものになっていました。つまり、これまでの受験生であれば文法学習の一環で身に付けた表現を今の受験生は身に付けられていないことを示唆しています。
もちろん、「そのようなものは…」と訳出した時点で、「そのようなもの」とは具体的に何であるのか、文脈をさかのぼって確認してみる意識も重要です。具体的な指示内容が見つからなければ、「そのようなもの」という解釈に無理があったと考えて軌道修正できるからです。この具体的な指示内容を確認しながら読むという意識の希薄さは、他の設問でも見受けられました。

最後に作文問題について簡潔に触れておきます。大問Ⅲは従来通りの和文英訳問題でした。大問Ⅳは「大学で研究をするうえであなたが最も重要と考えることを一つ挙げ、その理由を2点に絞って100語程度の英語で具体的に説明しなさい。」という自由英作文問題。2020年度に、海外留学の奨学金について大学生が問い合わせの手紙を書くという設定での自由英作文問題が出題されたことも考え合わせると、京都大学としては受験生に自分が大学でどう学び研究をするのか、ある程度具体的なイメージを持っていてほしいと考えているのではないかと思われます。
執筆者のプロフィール

▶河合塾英語科講師 佐野光宜(さの・みつよし)
深い洞察力や知見を授業・教材作成に生かし、大学入試改革や新たな学習手法の分析においても第一線で活躍。現役生対象の授業では「高3ONE WEX京大英語」、高卒生対象の授業では東大・京大、医進コースなどを担当。「京大入試オープン」模試や「高3ハイレベル国公立大英語」「京大英作文」などの教材作成にも携わっている。
