京都新聞・神戸新聞・産経新聞に河合塾によるコラム連載(第18回)
2022年10月13日
京都新聞、神戸新聞と産経新聞に、一昨年から導入された共通テスト傾向分析のほか、京都大・大阪大・神戸大など関西の難関大受験をテーマとしたコラムの連載しています。本連載では、河合塾近畿地区の講師やスタッフが大学受験に役立つ情報をお届けします。
今回ご紹介する第18回目は、河合塾数学科講師の西浦高志が京都大入試数学を振り返ります。
2022年度の京都大入試数学~記述解答は大学への「手紙」~
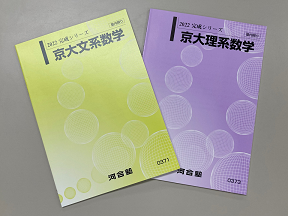
2022年は、新型コロナウイルス禍で人々が社会の中で以前の日常を取り戻すための苦労と努力が数多く見られた年ではなかったでしょうか。その中にあって、子供たちの学習環境や入試の実施にも、さまざまな工夫が見られたように思います。
22年の京都大学の入試(数学)においては、昨年に引き続き、出題された問題の難易度に配慮がありつつも、本質的に受験生に問いたい内容に変わりはありませんでした。昨年よりさらに工夫が見られた点は、文理ともに受験生に問いたい力が幅広く、明確であったということです。例年、文系は5題、理系は6題と、問題量が他大学と比べて多い印象ですが、出題の約半分は、基本的な考えの組み合わせかつ素朴な構成でありつつも、他に類がないものでした。題意をしっかり把握し、的確に計算する道具(数学の分野)を選択し、正確に、手際よく計算する力を問うていたように思います。この手の出題は今までもありましたが、今回は文理共に全体の中で、その比重は大きかったように思います。これは、難しい問題ばかり解けるように練習を繰り返している受験生に、基礎学力がいかに大事であるかを訴えているように感じます。実際に河合塾で実施している再現答案を分析すると、今回のような基本問題での計算ミスや、解法手順の悪さなどで差がつき、普段難しい問題で練習を積んでいる受験生でも基本が徹底されていないと、この時点で合格を逃していることが分かりました。難問と呼ばれるものは論理の展開の難しさや方法論が強調されがちであり、その中では、基本的な計算や公式の運用、素朴なアイデアが軽視されがちです。今一度、基本に返る学習を大切にしてほしいです。
一方で、例年通り誘導がない問題や色々な別解が発生する問題が出題され、受験生の自由な発想を引き出す工夫がなされていました。例えば、理系6番では、具体的な計算結果(実験)などから、何を読み取り(予想)、その正しさをどう説明(証明)するのか、ということが問われました。
改めて入試を振り返って感じることは、記述することの大切さです。限られた時間の中で、答案作成は大変な労を伴う作業ではありますが、思考過程を「伝える」ことにこそ「記述式試験」の本意があるのだと思います。普段、受験生の答案を目にする中で特に気になることは、式の羅列に終始しているものや根拠がデタラメなもの、文章が整理されておらず、内容が読み取れないものです。
京大は、「対話を根幹とした自学自習」をうたっている大学です。記述された解答は受験生から大学への大切なお手紙であり、受験生と京大の交流の絶好の機会とも言えるでしょう。手紙は伝わってこそ、その意味をなすものです。受験生は記述から、「相手」に思考過程という「熱意」と「誠意」が伝わるよう、しっかり解答を形にしてほしい。それが京大から「合格」という良い返事につながるのだと確信しています。
私たち講師も難関に挑む受験生に、ありったけの熱意と誠意を注いで参りたいと思います。
執筆者のプロフィール

▶河合塾数学科講師 西浦高志(にしうら・たかし)
大学受験科・高校グリーンコースでは東大・京大・医学部レベルの講座からハイレベル講座まで幅広く担当しています。また、「京大オープン模試」作成チーフや難関大学対策教材の執筆、河合塾マナビスの映像授業も担当し、多岐に渡り活躍しています。熱心な指導には定評があり、数多くの生徒から絶大な信頼を得ています。
※ 2022年10月時点
