京都新聞・神戸新聞・産経新聞に河合塾によるコラム連載(第23回)
2023年03月09日
京都新聞、神戸新聞と産経新聞に、一昨年から導入された共通テスト傾向分析のほか、京都大・大阪大・神戸大など関西の難関大受験をテーマとしたコラムの連載しています。本連載では、河合塾近畿地区の講師やスタッフが大学受験に役立つ情報をお届けします。今号ご紹介する第23回目は、河合塾・近畿地区医学科進学情報センター長の山口和彦が「23年度共通テストの概況」をお伝えいたします。
【お知らせ】
当Webサイトで掲載していました弊塾の寄稿は、今号をもって当Webサイトでの掲載は終了いたします。次号からは各紙のWebサイトにて掲載されます。※詳細は各紙へお問い合わせください。
2023年度大学入学共通テスト概況 ~平均点は数学が極端に上昇、理科は再び得点調整~
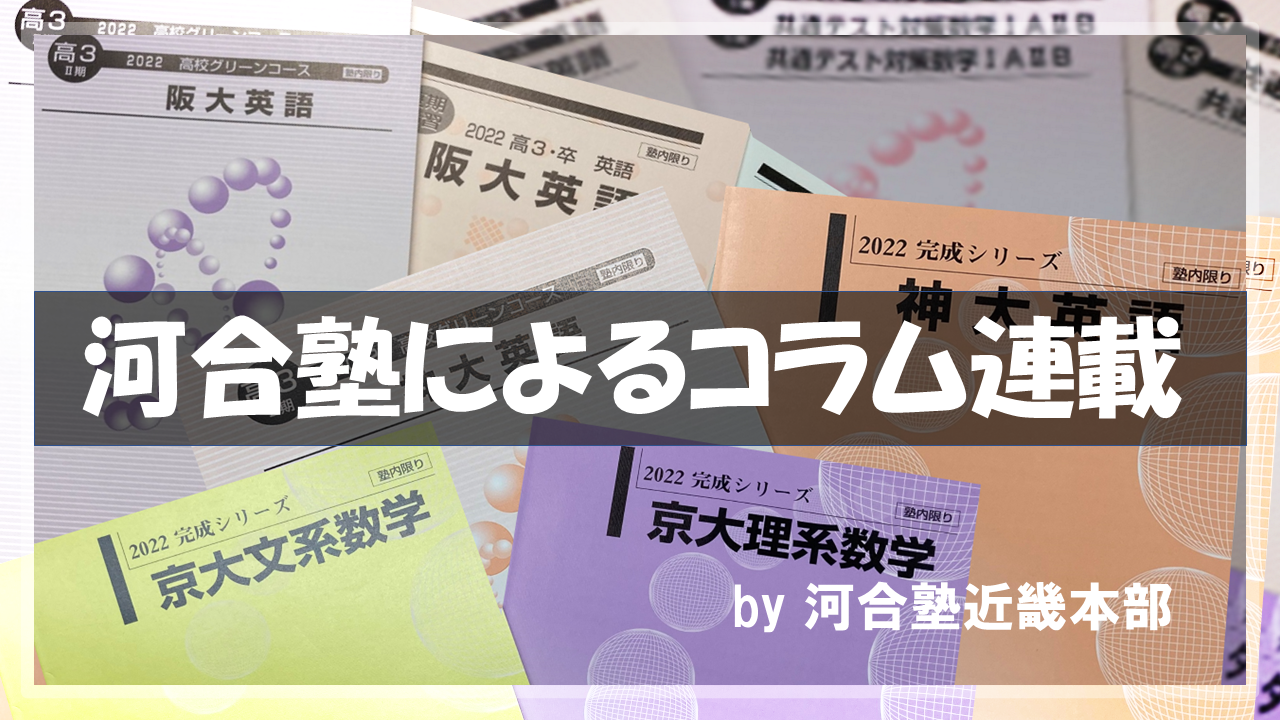
2023年1月14日(土)・15日(日)の2日間、今年で3回めとなる「大学入学共通テスト(以下、共通テスト)」が実施された。
今年の出願者数は512,581人で、これは前年より17,786人少なく、マイナス3.4%の出願者減少となっている。全国の18歳人口の減少率はマイナス2%程度だが、共通テスト出願者中の現役生比率はマイナス2.8%で、それより減少がやや大きい。一方、高卒生の減少率はマイナス6.7%となり、入試の中心は年を経るごとに現役生主体になりつつある。
2020年度まで続いた「大学入試センター試験(以下、センター試験)」を引き継ぎ、「問題考察」を揚げた「共通テスト」の平均点は、導入初年の2021年度は高かったが、2年めの2022年度には大きく下降し、先日実施された3年めの2023年度では再び上昇している。2023年度の総合平均点は、理系が900点満点中548点、文系は同じく530点(得点調整後の河合塾推定)。昨年に比較すると理系でプラス38点、文系でプラス23点の上昇幅になっている。
主な科目の平均点をみると、昨年は難度が高すぎると言われた数学は、ⅠA・ⅡBとも平均点が極端にアップしている。一方、理科は共通テスト初年に続いて、またしても科目間の平均点格差が大きく得点調整が実施された。過去3回の実施のうち2回が得点調整では、共通テストの問題作成の不安定さに受験生は戸惑うばかりだ。「考察を必要とする問題傾向」を反映するために、全体の難度が不安定になって受験生を惑わす傾向は、今後の共通テストでも継続するのだろうか。
国公立大前期の系統別志望動向をみると、医学部/医学科(対前年比111%)と薬学部(同107%)の志望者が大きく増加している一方、同じ医療系でも看護の志望者は減少している(同97%)。また、農学部は獣医学科の志望者(同113%)が増加しているが、生物生産系は横ばい(同103%)となった。理系で定員がもっとも多い工学部は志望者が減少(同97%)、理学部はほぼ横ばい(101%)となっている。文系においては経済学部志望者(同104%)が法学部(同98%)よりやや増加している。また、コロナ禍に海外連携する職業への不安から、外国語学部の志望者は減少傾向が続く(同86%)。文系学部では理系学部の医学科や薬学部のような突出して志望者が増加した学部はなく、むしろ減少傾向となっている。この学年の受験生は高校入学時以来の「コロナ学年」であり、文理分けを含め進路選択には新時代の自分を取り巻く環境や時代のトレンドが志望に大きく影響していると思われる。
ここ3年の傾向を見る限り、共通テストはまだまだ不安定な要素が多い。それでも受験生は様々な情報を検討し、熟考して出願大学を決定したことだろう。次はいよいよ出願した大学の二次試験だ。最大集中力での学習が運命を決める。我々も、全力でそんな受験生をサポートしていきたいと考えている。
執筆者のプロフィール

▶河合塾近畿地区医学科進学情報センター長 山口和彦(やまぐち・かずひこ)
河合塾入職後、長年第一線で受験生の指導を行う。医学科志望者だけでなく、東大・京大志望から私立大志望まで幅広い生徒を担当。指導した生徒は延べ3,000人を超える。2016年から近畿地区医学科進学情報センター長として、近畿地区の全校舎の医学科受験指導を統括。河合塾を代表する医学科受験指導のプロフェッショナル。
※2023年3月時点
